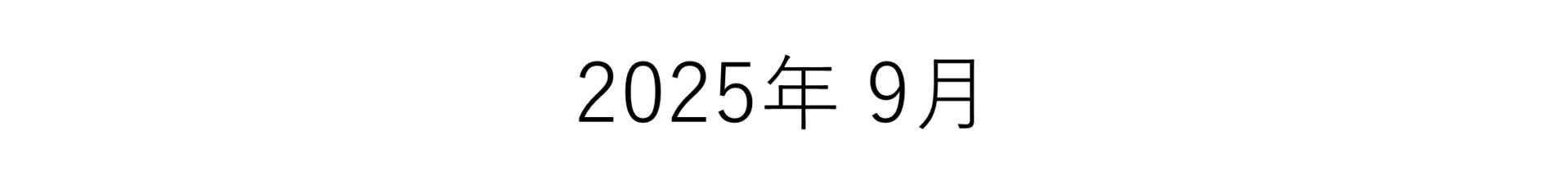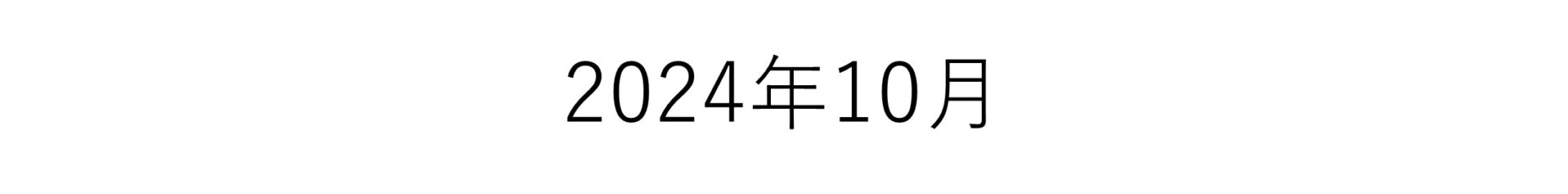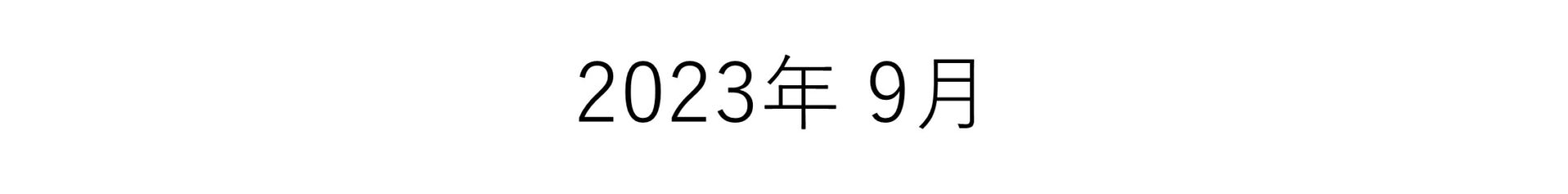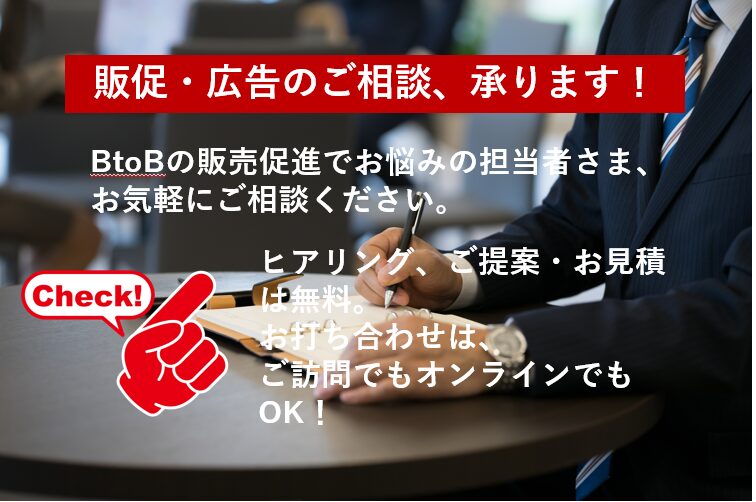はじめに
2025年、日本の住宅市場は依然として多くの課題を抱えています。資材価格の高止まり、人材不足、人口減少による需要の変化、金利動向の影響など、不確実性の高い状況が続いています。その中で、政府は住宅の省エネルギー性能を高めることを政策の柱に据え、国土交通省・環境省・経済産業省が連携してさまざまな補助金制度を展開しています。
これらの制度は、消費者にとっては「家計を助けながら快適な住環境を手に入れるための手段」であると同時に、工務店やリフォーム会社、建材メーカーや設備メーカー、不動産会社、マンション管理会社など幅広い事業者にとっても営業・販促活動の強力な支援材料となります。
展示会でも
「この製品は補助金の対象になりますか?」
「制度を使えばどれくらい安くなるのですか?」
といった質問が多く、補助金活用は製品説明と並ぶ大きな関心事項になっていました。制度を理解し、具体的に説明できることは商談獲得や成約率向上に直結していると言えます。
住宅省エネ2025キャンペーンの概要
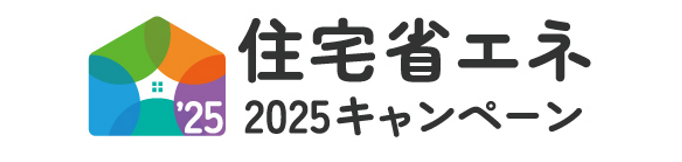 住宅省エネ2025キャンペーンは、環境省が主導する大規模な制度で、断熱窓、断熱材、高効率給湯器、太陽光発電、蓄電池などが対象です。
住宅省エネ2025キャンペーンは、環境省が主導する大規模な制度で、断熱窓、断熱材、高効率給湯器、太陽光発電、蓄電池などが対象です。
例えば窓改修の場合、内窓の新設、外窓交換、ガラス交換といった複数の方法が補助対象工事となっています。内窓設置は比較的短期間で施工でき、費用も抑えられるため、補助金を活用して提案しやすい工事です。外窓交換は工期がかかりますが断熱効果が高く、光熱費削減効果も大きいことから、長期的なメリットを強調できます。
断熱材については、壁・屋根・床と施工部位ごとに補助額が異なり、性能基準を満たす製品を使うことが条件です。給湯器はエコキュートやハイブリッド給湯器、家庭用燃料電池「エネファーム」などが対象で、顧客のライフスタイルに合わせた選択が可能です。太陽光発電や蓄電池は、停電時のレジリエンス強化としての訴求も有効です。
補助額と予算規模
窓リフォームは一戸あたり最大200万円、高効率給湯器は導入する高効率給湯器に応じて1台あたり6万円から16万円が補助されます(2025年10月時点)。全体の予算は数百億円規模で設定されていますが、先着順のため、予算上限に達すると年度途中でも申請受付が打ち切られる可能性があります。過去のキャンペーンでは、開始から半年で予算が上限に達し、秋以降の申請が受け付けられなくなった事例もありました。
補助金の予算規模は年度ごとに増減があり、近年は省エネ需要の高まりを背景に拡充傾向が見られます。
図1:住宅省エネ補助金予算推移(2022〜2025年度)

出典:環境省『住宅省エネ2025キャンペーン』等
図からも分かるように、制度全体の予算は変動を繰り返しながら拡充されており、展示会でも「予算消化のスピード」を気にする来場者が多く見られました。年度後半の申請タイミングを意識した相談も増えています。
補助金訴求の実践ポイント
営業現場では、
「補助金があるからお得」ではなく
「光熱費削減額 × 補助金でどれだけ初期負担が減るか」
を数値で示すことが重要です。
展示会で取材した窓メーカーの担当者は「補助金を活用した提案を始めてから、問い合わせが前年比130%に増えた」と話していました。
こどもエコすまい支援事業
 国土交通省が所管する「こどもエコすまい支援事業」は、子育て世帯や若年夫婦世帯を対象とする制度で、注文住宅の新築や新築分譲住宅の購入については1住戸につき最大100万円、リフォームは実施する補助対象工事および工事発注者の属性等に応じて5万円~60万円の補助が受けられます(2025年10月時点)。
国土交通省が所管する「こどもエコすまい支援事業」は、子育て世帯や若年夫婦世帯を対象とする制度で、注文住宅の新築や新築分譲住宅の購入については1住戸につき最大100万円、リフォームは実施する補助対象工事および工事発注者の属性等に応じて5万円~60万円の補助が受けられます(2025年10月時点)。
展示会でも、対象世帯条件が重要である点や、家族構成を伺いながらその場で試算を提示する営業手法が注目されていました。工務店の営業担当者は「補助金に詳しい会社だと安心してもらえる」と話しており、制度理解が顧客の不安解消や契約の後押しにつながっています。
不動産会社にとっても分譲住宅販売の追い風です。モデルルームで「補助金を活用すれば実質負担はこれだけ減ります」と説明すると、若い世帯の購入意思決定が早まります。展示会では「子育て世帯向けの補助金対応住宅」の展示が注目を集めていました。
中古住宅ZEH改修支援制度
 中古住宅市場の活性化を目的とする「ZEH改修支援制度」では、既存住宅を購入して断熱改修や高効率設備導入を行い、再生可能エネルギーを組み合わせることで、個人申請の場合、補助対象経費の1/3以内、上限300~400万円が交付されます(地域区分により上限額が異なる:2025年10月時点)。
中古住宅市場の活性化を目的とする「ZEH改修支援制度」では、既存住宅を購入して断熱改修や高効率設備導入を行い、再生可能エネルギーを組み合わせることで、個人申請の場合、補助対象経費の1/3以内、上限300~400万円が交付されます(地域区分により上限額が異なる:2025年10月時点)。
業界別の補助金活用事例
ある不動産会社では「中古購入+補助金リフォーム」という提案により成約件数が前年比1.4倍に増えました。リフォーム会社でも「補助金を使えば自己負担が減り、月々の返済負担も軽くなる」という説明が中古住宅購入検討者の後押しにつながったという声がありました。
都市部では築30年以上のマンションストックが増加しており、断熱改修や設備更新の需要は確実に拡大しています。補助金を活用したリノベーション提案は、不動産業界全体にとっても重要な差別化戦略になっています。
フラット35Sと資金計画
表1:住宅省エネ補助金制度の概要

出典:環境省、国土交通省、SII、住宅金融支援機構(2025年公表資料) ※2025年10月時点での情報です。申請前に各制度の募集要項で詳細をご確認ください。
住宅金融支援機構の「フラット35S」は、省エネ性能を満たす住宅に対して当初5年間、金利を0.25〜0.75%優遇します。
営業現場では「補助金で初期費用を軽減し、さらにローン優遇で返済も抑えられる」という説明が効果的で、展示会でも資金計画と補助金を併せて説明できる営業担当者が信頼されているという声が聞かれました。金融機関と連携した不動産会社は「資金+性能+補助金」の三点セットで顧客の納得感を高めています。
展示会で見られた活用事例と注意点
展示会取材を通じて、補助金を活用した展示手法や商談の工夫が目立ちました。窓メーカーは「補助金対象」の掲示で来場者からの質問が増え、給湯器メーカーは対象機種リストの配布により名刺交換数が1.5倍に増加。不動産会社は中古リフォーム事例動画の上映により滞在時間を伸ばし、管理会社は共用部改修事例の展示で管理組合役員からの相談を獲得していました。
 補助金活用には注意点もあります。書類不備による差し戻し、対象外製品の誤提案、写真撮影の不備、予算の早期消化による受付終了などが挙げられます。工務店の担当者は「製品ラベル写真が不鮮明で再提出になった」と話しており、申請チェックリストを整備し施工現場と共有することが重要です。
補助金活用には注意点もあります。書類不備による差し戻し、対象外製品の誤提案、写真撮影の不備、予算の早期消化による受付終了などが挙げられます。工務店の担当者は「製品ラベル写真が不鮮明で再提出になった」と話しており、申請チェックリストを整備し施工現場と共有することが重要です。
営業現場での説明事例
補助金を活用した説明は、以下の三段構成が効果的です。
1.「光熱費や寒さに困っていませんか」と課題を提示
2.「断熱窓や高効率給湯器で改善できます」と解決策を提示
3.「さらに補助金を利用すれば実質負担がこれだけ減ります」と数字を示す
この流れは分かりやすく、展示会でも来場者の理解が早いという声が多く聞かれました。不動産会社は「補助金とローン優遇を組み合わせると月々の返済が約○万円減る」と説明し、管理会社は「共用部改修の一世帯あたり負担が△万円軽減される」と伝えることで、説得力のある案内につながっています。
まとめ
2025年の住宅省エネ補助金は、工務店や建材メーカー、不動産会社、設備メーカー、マンション管理会社など幅広い業界にとって成果を高める制度です。工務店はリフォーム受注を拡大でき、メーカーは製品訴求力を強化でき、不動産会社は中古住宅販売で差別化を図れます。展示会や営業現場で補助金を分かりやすく説明できる企業こそ、顧客から選ばれ続けるでしょう。HOUSEMEDHIA編集部は、今後も展示会取材を通じて現場で役立つ最新情報を発信していきます。
2025年11月

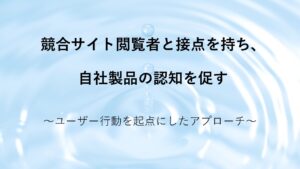

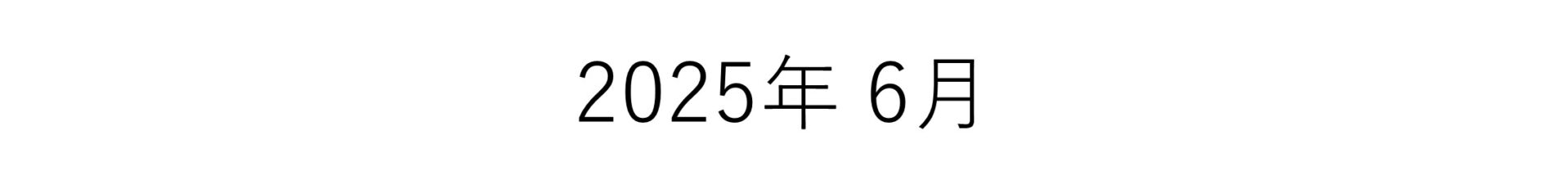
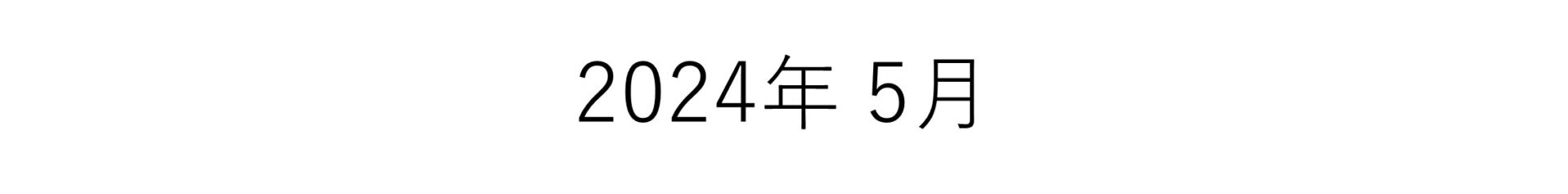
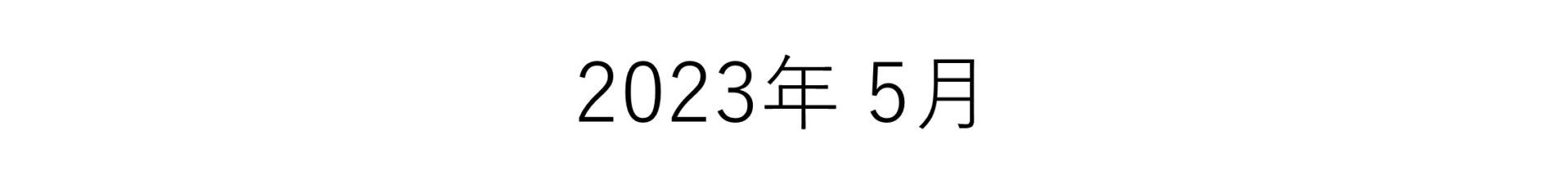

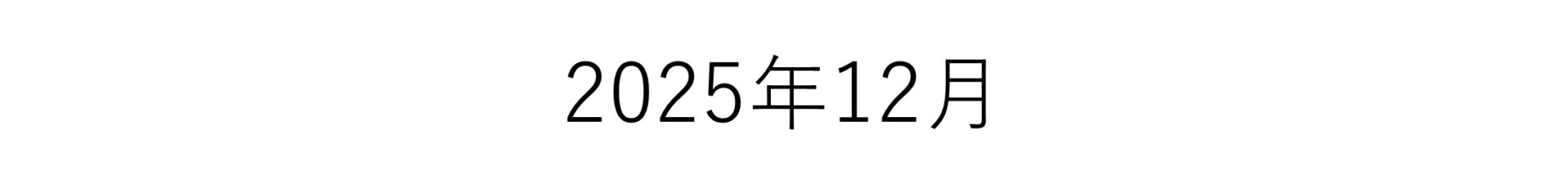
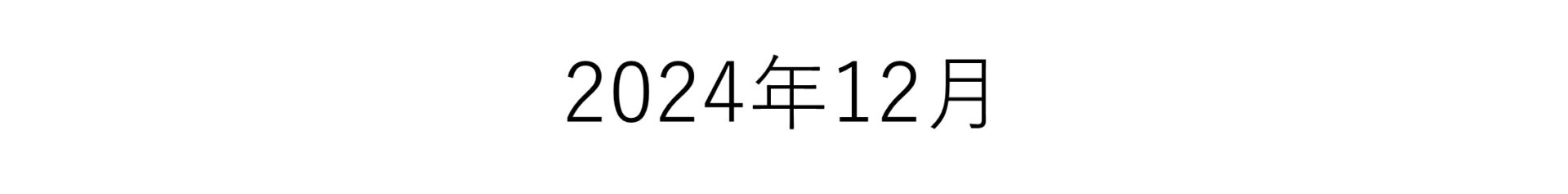
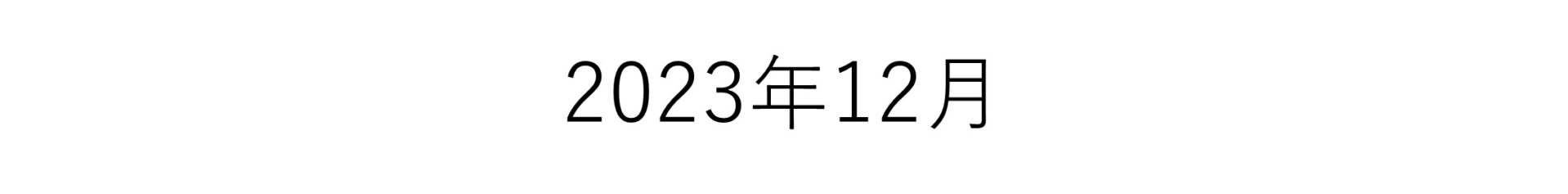
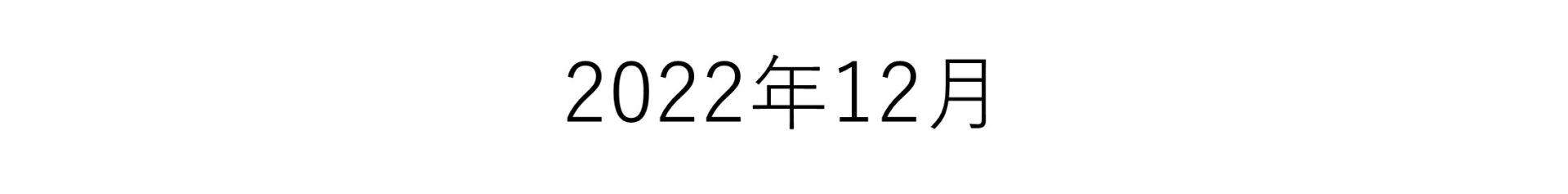
1.jpg)