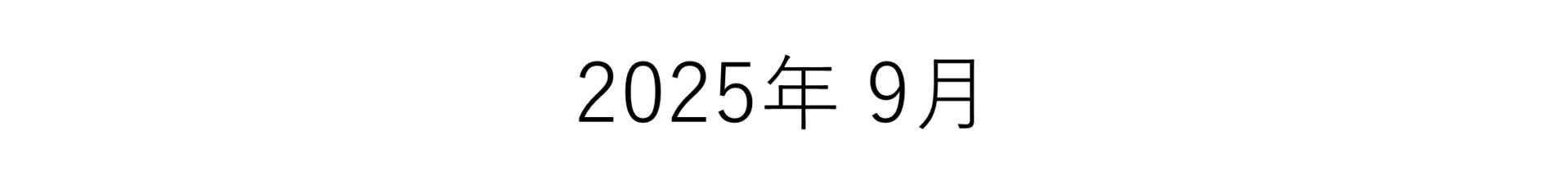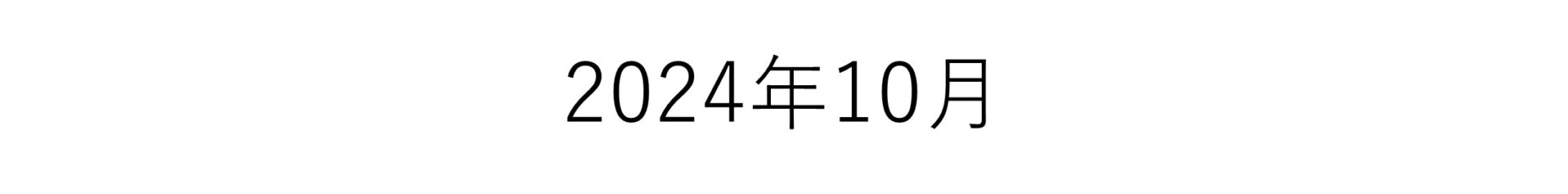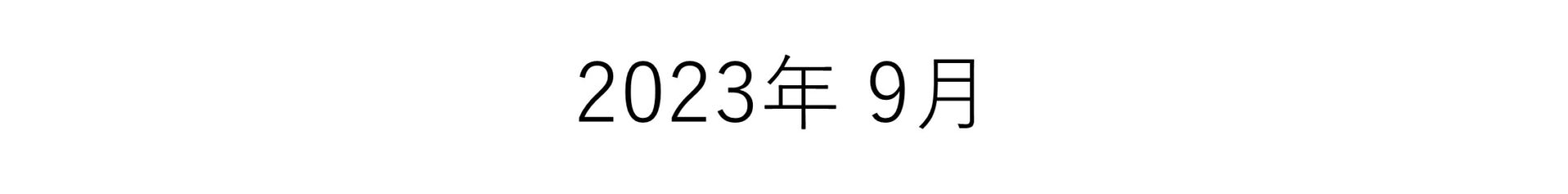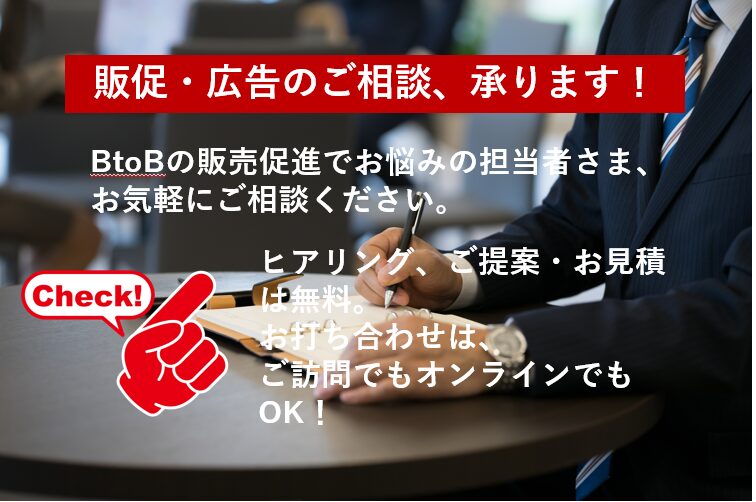日本リビング保証株式会社では、主にハウスメーカーや工務店、仲介会社向けに、住宅領域に特化した保証サービスを提供しています。「建物長期保証」「住宅設備保証」「地震保証」をメインに、事業者が自社の住宅を競合他社と差別化したり商品力向上を図りたいといった声に応える保証内容になっています。特に住宅オーナーとの関係性を重視した保証制度を構築している点が特徴です。
製品検索
住宅領域を幅広く保証する
住宅領域を幅広く保証する
「建物長期・住宅設備・地震保証」日本リビング保証株式会社
製品概要
製品のポイント
- 1
建物長期保証は、構造耐力の主要な浸水防止の部分を初期20年、それ以降は最長60年まで延長可能で、住宅オーナーとの長期にわたる接点を保証という形で維持できる
- 2
住宅設備保証は、10年保証後も延長可能で、回数無制限で無料保証を行う。その付加価値により競合他社との差別化も図ることが可能
- 3
地震保証なら、住宅オーナーが建物の品質を住宅性能表示における耐震等級だけで判断するのは難しい中、保証をサービスとして提供することで事業者の建物をアピールできる
おすすめしたい利用者
住宅メーカー、工務店、仲介会社など
会社情報
| 会社名 | 日本リビング保証株式会社 |
| 製品名 | 建物長期・住宅設備・地震保証 |
| サイトURL | https://jlw.jp/business/solutions/ |

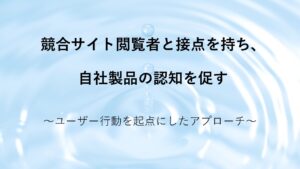

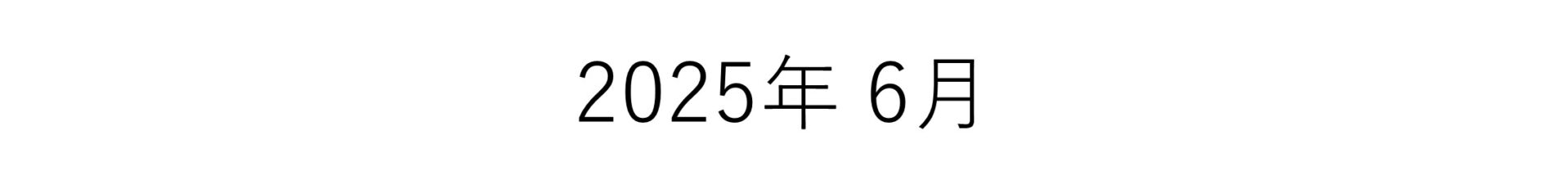
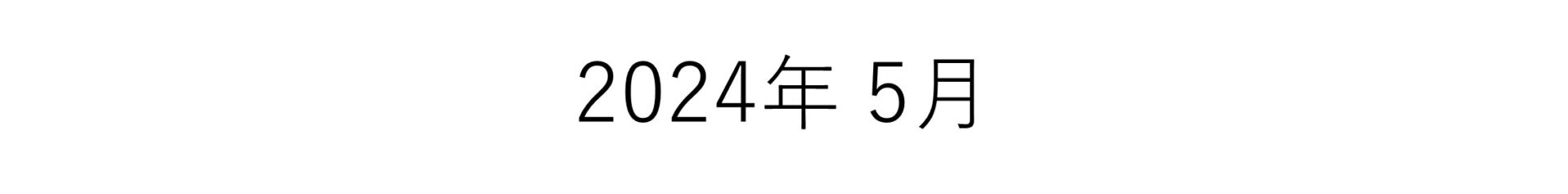
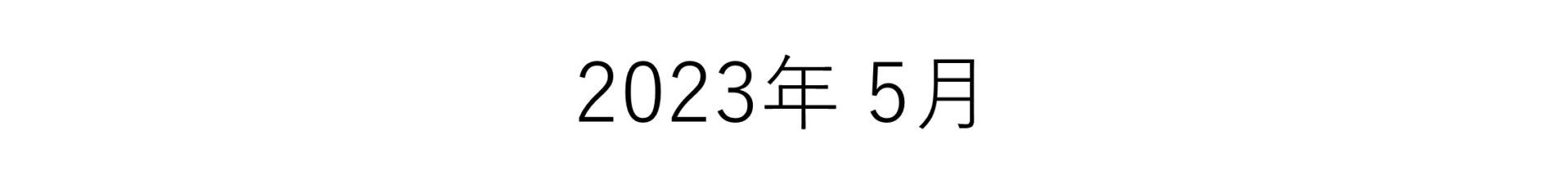

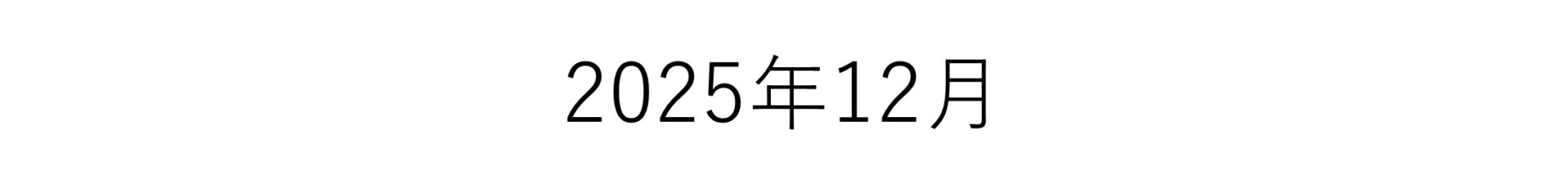
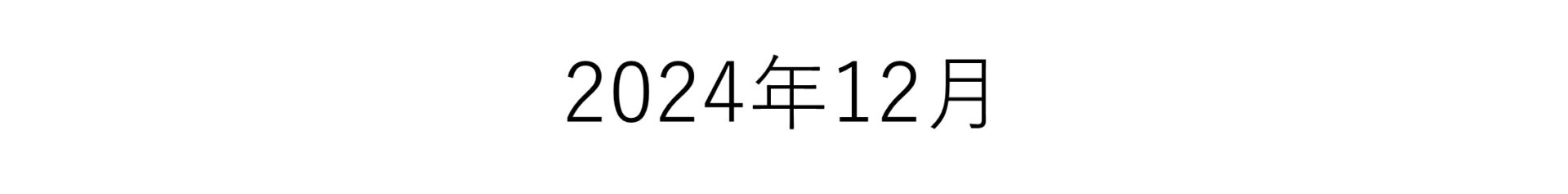
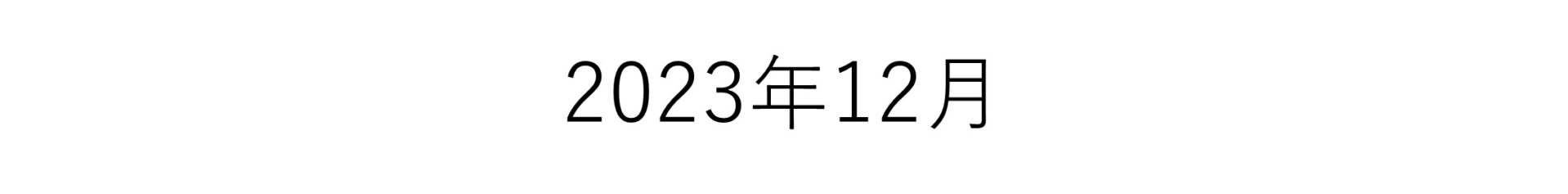
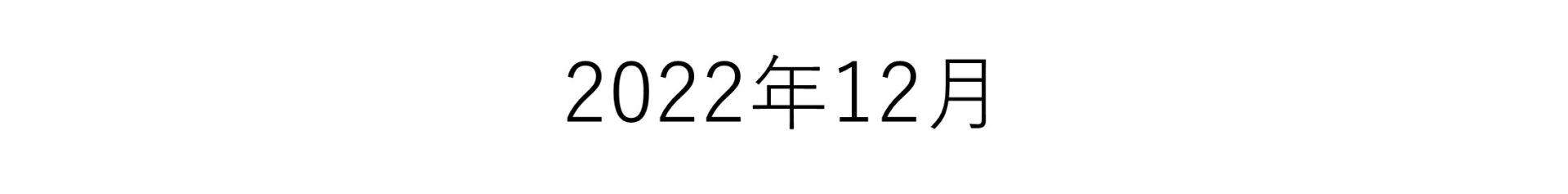
1.jpg)